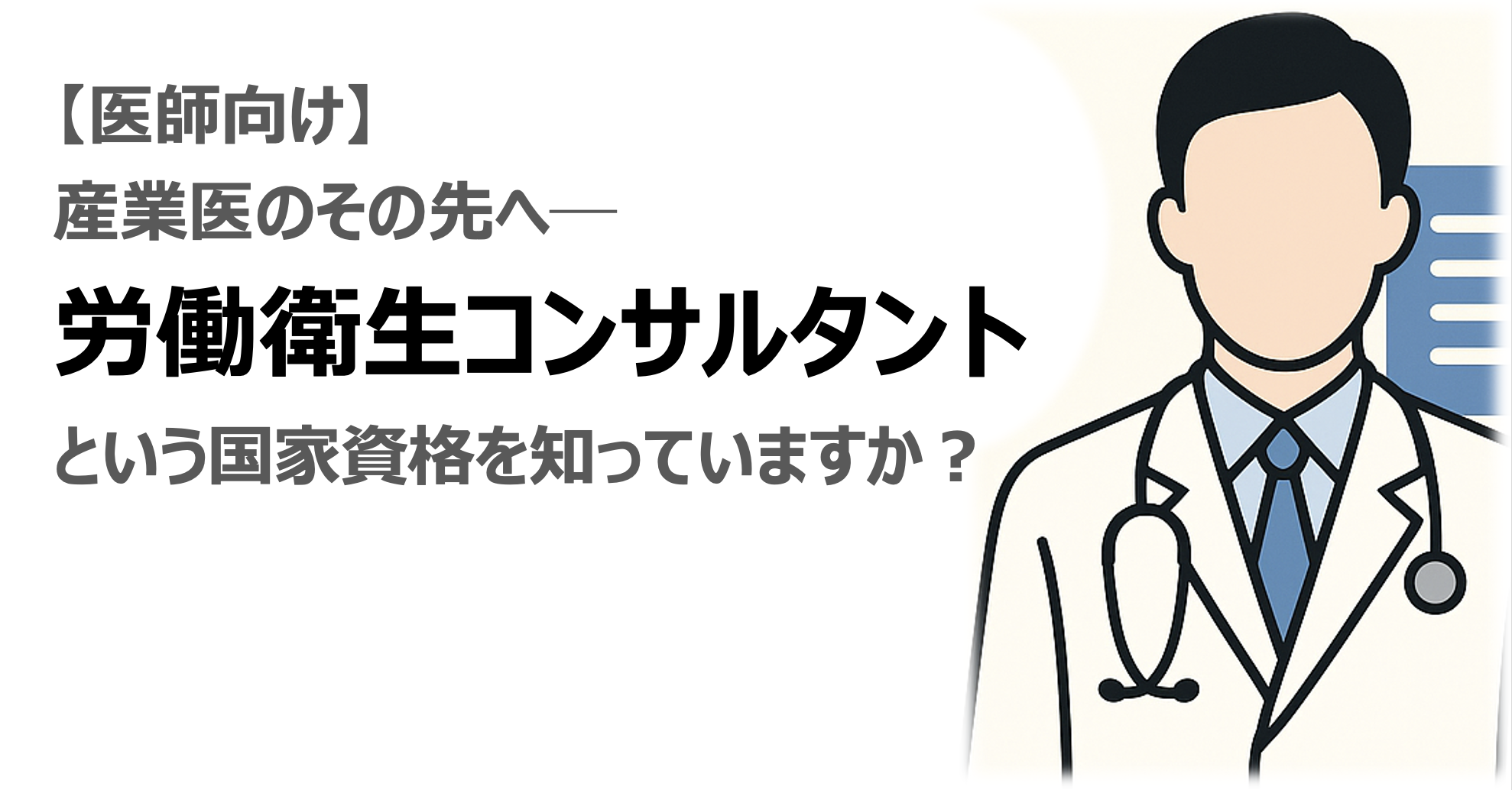Dr.しーぼると(MD, PhD)
外科医|疫学研究者|産業医・労働衛生コンサルタント
地方旧帝大を卒業後、「東京の御三家」で初期研修を行い、その後は市中病院で外科医として診療に従事。基礎系博士号を取得し、現在は公衆衛生系大学院にて疫学研究を行う一方、産業医・労働衛生コンサルタントとしても勤務。
「基礎医学」「臨床医学」「社会医学」を横断してきた経験を活かし、疫学に関するテーマを初学者にもわかりやすく解説します。
労働衛生コンサルタントという国家資格をご存知でしょうか?
社会医学系のラボに所属している人や、産業医資格をすでに有している人はすでにご存知かもしれませんが、ほとんどの医師にとって初めて聞く資格ではないでしょうか?
コンサルタントと聞くと、なんだか胡散臭いと感じる人もいるかもしれません。しかし、日本にはコンサルタントの名を有した国家資格がいくつかあり、労働衛生コンサルタントはその一つです(キャリアコンサルタントなんていうのもあります)。企業で勤務されている方には労働安全コンサルタントの方が馴染みがあるかもしれませんが、一般的に医師が有するメリットがあるのは労働衛生コンサルタントです。
労働衛生コンサルタントは、産業医の経験を活かして企業の労働衛生体制により深く関与したい医師にとって、有力なキャリアオプションです。制度上は医師に限定された資格ではありませんが、実際には多くの産業医が“ステップアップ”の手段として受験している国家資格です。特に、医師かつ労働衛生コンサルタントであれば、産業医資格を“永年保有”できるという点は非常に大きなメリットであり、制度的にも実務的にも注目すべき特徴があります。
この記事では、大学院生に限らず、若手臨床医の方にとっても有用かもしれない、労働衛生コンサルタントについて、概論でお伝えします。
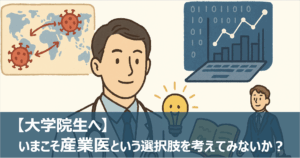
労働衛生コンサルタントとは?
労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法第82条に基づいて設けられた国家資格で、企業の労働衛生に関する診断・指導・助言を行う専門家です。企業からの依頼を受けて、法的な観点や専門知識に基づいた支援を行います。
この資格には2つの区分があり、それぞれ受験対象者や試験科目が異なります。
- 保健衛生区分:医師、保健師、薬剤師、歯科医師、看護師など、保健衛生に関する実務経験を有する者が対象
- 労働衛生工学区分:作業環境測定士や技術士など、工学的視点からの労働衛生支援が可能な者が対象
労働衛生コンサルタントは企業にとって必須の配置義務はなく、コンサルタント自身も特定の企業に常駐する必要がありません。制度的には産業医とは全く別の位置づけにあります。
産業医と労働衛生コンサルタントの違い
ここまで読んでみて、同じ産業衛生に関する産業医との違いが釈然としない方が多いのではないでしょうか?
私もそうでしたし、実際の労働衛生コンサルタントの二次試験(口述試験)では、受験者が産業医であれば必ずと言っていいほど、産業医と労働衛生コンサルタントとの違いを聞かれます(多くの参考書でそのように書いてありますし、実際に私もそうでした)。
制度上の両資格の違いを下記のテーブルにまとめます。
| 労働衛生コンサルタント | 産業医 | |
| 資格 | 国家資格(医師以外も可) | 指定の研修等の条件を満たした医師 |
| 配置義務 | なし(任意) | 労働者50人以上の事業場 |
| 主な活動範囲 | 法令に基づく助言、体制評価、監査的支援など | 健康管理、職場巡視、面談など |
| 業務の位置づけ | 外部専門家としての“コンサルティング職” | 労働安全衛生法に基づく“社内職” |
| 活動形態 | 単発 | 定期的(常勤・嘱託) |
一言で言うと…
- 産業医は、企業の一員として、健康管理を中心とした5管理を定期的に行う
- 労働衛生コンサルタントは、企業外の独立した立場から、5管理を包括的に単発で行う
5管理とは?
労働安全衛生法に基づく労働衛生管理の基本的枠組みを構成する5つの柱であり、以下のように分類されます。
◼️ 作業環境管理:有害物質や騒音、温湿度などの職場環境要因を測定・改善する管理。
例:換気、局所排気装置の設置。
◼️ 作業管理:作業手順や労働時間、姿勢など、作業そのものを安全・健康的に行えるようにする管理。
例:作業時間の短縮、交代制導入。
◼️ 健康管理:労働者の健康状態を把握・管理し、健康障害の予防や早期対応を行う管理。
例:健康診断、面接指導。
◼️ 労働衛生教育:労働者に対し、安全衛生に関する知識・技能を教育し、自主的な健康管理を促す管理。
例:新入社員研修、危険有害業務従事者教育。
◼️ 総括管理:上記4つの管理を総合的に調整・監督する管理。事業者や衛生管理者、産業医などが連携して推進します。
作業環境管理・作業管理・健康管理の産業保健の特に基礎となる3つを「3管理」と呼びます。
上記のような違いは明文化されていますが、後述する通り、労働衛生コンサルタントの受験者の大半が産業医であることを考えると、実務上はかなりの部分が重複しており、明確な線引きは難しい(というか、不要)のが実態だと思います。
実際の受験者はほとんどが医師─産業医資格との深い関係
制度上は医療職に限られた資格ではないものの、保健衛生区分の受験者の大多数は医師、特に産業医経験者です。実務ではほぼ「産業医の次のステップ」もしくは「上位資格」として位置づけられているのが実情です。
さらに注目すべきは、医師が労働衛生コンサルタント(保健衛生)資格を取得すると、産業医資格の“永年保有”が可能になることです。日本医師会の産業医制度では、一定期間ごとに更新が必要であり、そのたびに研修や書類提出が求められます。一方、労働衛生コンサルタントの医師であれば、そのような更新手続きを不要として、恒久的に産業医として活動することが認められています。
この制度的利点から、「もともと日本医師会認定産業医だったが、更新制度の煩雑さを避けたい」との理由で、労働衛生コンサルタントに移行する医師も少なくありません。特に嘱託産業医やフリーランスで複数企業を担当する医師にとっては、資格の“更新不要”というメリットは非常に大きいのです。
受験について
試験と認定(登録)は、厚生労働大臣指定機関である公益財団法人 労働安全衛技術試験協会(https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokaieisei/)が管轄しています。
受験資格
受験資格については、27項目がありますが、下記の通り医師は無条件で受験できます。
“医師法(昭和23年法律第201号)第9条の医師国家試験に合格した者、同法第36条第1項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第41条の規定により医師免許を受けることができる者”(労働安全衛生法第82条)
試験科目
◼️ 一次試験
| 試験科目 | 方法 | 出題点(配点) | 試験時間 |
| 労働衛生一般 | 択一式 | 30問(300点) | 120分 |
| 労働衛生関係法令 | 択一式 | 15問(150点) | 60分 |
| 専門科目 ・健康管理 ・労働衛生工学 | 記述式 (試験の区分に応じて1科目を選択) | 2問(300点) | 120分 |
産業医資格になるのは保健衛生区分ですので、医師は保健衛生で受験する人は大半だと思います。この場合、専門科目は「健康管理」になります。
◼️ 二次試験
保健衛生区分の場合な、「労働衛生一般」と「健康管理」です。
「法令」は明記されていませんが、法令は「労働衛生一般」と「健康管理」に密接に関連していますので、実際には法令の内容も把握しておく必要があります。つまり、一次試験と同じです。科目ごとに質問されるのではなく、あるテーマについて科目横断的に答えなければなりません。
口述試験は15分間で、グループではなく個人ごとに行われます。
免除科目
こちらも複数の免除科目の要件が定められていますが、医師に関しては主に下記の2つです。
まず、医師であれば無条件に、「労働衛生一般」と「健康管理」が免除されます。つまり、「労働衛生関係法令」(通称「法令」)のみの受験を選択することができます。
さらに、医師であり、かつ「厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習※を修了した者」は筆記試験の全科目を免除できます。つまり、二次試験の口述試験のみの受験を選択できます。
※「厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習」とは、下記の3つが該当します。
① 公益社団法人日本医師会が行う「産業医学講習会」
② 公益社団法人日本歯科医師会が行う「産業医学講習会」
③ 学校法人産業医科大学が行う「産業医学基本講座」
厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)の③の学校法人産業医科大学が行う「産業医学基本講座」とは、 産業医科大学の夏期集中講座である「産業医学基礎研修会」とは異なります。
両者の違いについては、【大学院生へ】いまこそ産業医という選択肢を考えてみないか?もご参照ください。
もちろん、試験科目を免除できる権利はありますが、免除しないという選択肢もありです。前述のように、法令のみでは15問のみで合否を決める必要があります。医師であれば健康管理の知識はありますし、労働衛星一般は総じて法令よりも難易度が低いです。総合点で6割を超える戦略としては、あえて科目免除しないというのも有効でしょう。
ただ、私は、試験対策に割く時間を最小限にしたかったため、法令のみで受験しました。
試験会場
一次試験は下記の6か所です。受験申請時に指定します(東京都と愛知県は詳細な場所は選択できないようです)。
- 北海道安全衛生技術センター
- 東北安全衛生技術センター
- 関東安全衛生技術センター
- 東京都(ベルサール渋谷ファースト又は関東安全衛生技術センター東京試験場)
- 愛知県(中部安全衛生技術センター又は東海市芸術劇場)
- 兵庫県(神戸サンボーホール)
- 中国四国安全衛生技術センター
- 九州安全衛生技術センター
二次試験は、下記の2か所です。こちらも最初の受験申請時に指定します。
- 東京:東京都(新宿NSビル)
- 大阪:大阪府(エル・おおさか)
試験日
2025年度(令和7年度)の試験日情報を掲載します。
一次試験は、令和7年10月21日(火)です。もちろん試験会場同日です。
受験申請の期間は、7月1日(火)~7月31日(木)です。
12月上旬に一次試験の合格発表があり、合格者は二次試験日の知らせが届きます。
- 東京:2026年1月27日(火)~1月30日(金)のあらかじめ指定する日時
- 大阪:2026年1月14日(水)~1月15日(木)のあらかじめ指定する日時
東京の方が2週間ほど後なので、受験追い込み型の人は東京にすべきかもしれません。私は東京会場の日程が他の学会とかぶっていましたので、大阪会場で受験しました。
最終合格発表は、2月下旬にあります。まずはHP上で受験番号が公開され、追って郵送で正式な合否通知が届きます。
申請については、私が受験した際には申請書を郵送する形式でした。直前まで産業医研修で自宅を空けていましたので、帰宅してバタバタと書類を用意した記憶があります。
ただ、現在はオンライン申請も可能となったようです(https://www.exam.or.jp/m/index.html/)。
また、今年度(令和7年度)より、申請書に「経歴」を記載する欄ができたようです。これまで、二次試験では必ずまずは始めに産業保健の職務経験を聞かれていましたし、これほど多数の実務経験が受験要件にあるのに、むしろなぜこれまで経歴情報を書かなくてよかったのかが不思議でした。
難易度
労働衛生コンサルタントの資格の合格率は「およそ3割」といわれています。下記表は昨年度(令和6年度)のものです(公益財団法人 労働安全衛技術試験協会HPより: https://www.exam.or.jp/h_gokakuritsu/)。

上記表の口述試験受験者数の()内は筆記試験全部免除者数です。二次試験では、半数以上が一次試験免除者(=産業医学基本講座等の修了生)であることがわかります。バイアスですが、彼らはすでに産業医として実績を積んでいる方がほとんでしょう。そんな人たちが大半の試験であってこの合格率なのは、比較的難しい部類に入るのかもしれません。
昨年度の筆記試験の合格率が例年よりも低いのは、問題の難易度が上がったためだと考えられます。合格基準は、一次試験では正解率がおおむね6割(ただし、1科目でも4割を下回った場合は不合格)とされています。この漠然としたボーダーラインが、昨年度は下がっていたようです。多くの医師が法令のみを受験しますが、15問中8問以上正解で一次試験を突破した報告がX等で散見されました。もし厳密に6割ボーダーで切っていたら、もっと合格率が低かったことでしょう。
まとめ
医師が労働衛生コンサルタント(保健衛生)を取得することには、産業医資格を同時に所有することができるというメリットがあります。
多くの産業医がとるルートである日本医師会認定産業医の取得には、金銭的・時間的に多大なコストがかかります。また、更新していくとなるとそれが一生涯続きます。また、集中研修に応募しても数年連続で抽選に漏れることもザラにあります。労働衛生コンサルタント試験の合格は、これらのデメリットを回避し、産業医資格を保有することができるのです。
私の個人的な意見ですが、労働衛生コンサルタント資格の取得に最も恩恵があるのは、非産業医の医師でしょう。すでに産業医資格を保有されている方は、ある意味の上位資格という形で取得されることになると思います。
労働衛生コンサルタントという国家資格は、医師が産業保健に専門的に関わるうえで、制度的にも実務的にも極めて有利な立ち位置を提供してくれます。とりわけ、これから産業医資格を目指す医師にとっては、「更新不要」「一発合格で完結」「専門性の証明」といった高いコストパフォーマンスを持つ、非常に実用的な選択肢です。
一方で、そのぶん試験は決して甘くはありません。国家資格としての体系的な知識と論理的思考が求められる場面も多く、受験には相応の準備が必要です。今後、受験対策のノウハウや勉強方法についても発信していく予定ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。
制度を正しく理解し、自身のキャリア戦略に沿った選択を。産業保健の未来を担う「戦略的専門家」としての一歩を踏み出してみませんか。
Dr.しーぼると(MD, PhD)
外科医|疫学研究者|産業医・労働衛生コンサルタント